文楽の初心者向け本はいっぱいあるけれど、中級者にステップアップするための本や中級者向けの本はあまりない。そんな私の不満に自ら答える「文楽中級者向け」ブックガイド第2弾。今回は、ついつい流し見してしまう人形の演技をじっくり考えるきっかけを作ってくれた本を紹介したい。
今回取り上げるのは、10年以上前に亡くなった往年の名人の談話ながら、いまなおリアルに共感でき、理解でき、納得できるという驚くべき1冊。
いままでに買った文楽の本の中で、もっとも買ってよかったと思う本でもある。持ってない方は、次に文楽行ったときに絶対買ってほしい。
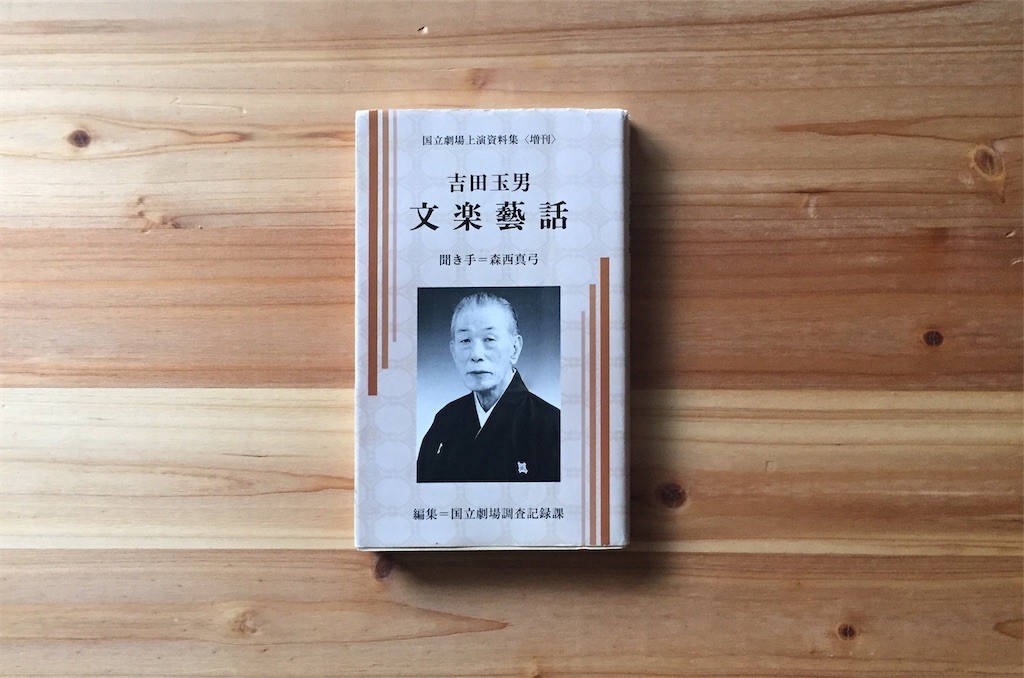
吉田玉男・森西真弓=著、国立劇場調査養成部調査記録課=編『吉田玉男 文楽藝話』日本芸術文化振興会/2007
戦後を代表する人形遣い・初代吉田玉男(1919-2006)の芸談聞き書き本で、一般書店には流通しておらず、国立劇場・国立文楽劇場の売店でのみ販売されている。
32の有名演目について、玉男師匠が自分の工夫や修行時代の思い出を語っていくというもので、簡素な装丁の新書サイズの本ながら、現代の人形演技を見る上での超超超必携書だと思う。
■
この本を読んで一番驚いたのは、人形の演技とはここまで理論に支えられているものなのかということ。
私は、人形の演技には決められた伝統的な振り付けがあって、それをいかに正確に美しくこなしていくかで巧拙が現れていくものだと思っていた。だから、いかに稽古するかが重要で、芸談も、そのためにどういう修行をしたとか、いかに耐えたかという、努力論や精神論の話になるのかと思っていた。極端に言うと、頭の上に水を張ったタライを乗せて徹夜で踊りの稽古をしたとか、そういう感じの。しかし、この本ではそういった話は全くされていない。浄瑠璃(本)を読み込み、それをどう表現するか、舞台での実践が重点的に語られている。
だから、この本を読んだときにはその理論性にものすごくびっくりした。玉男師匠の理論とは、個人的にそう思ったからという意見という意味ではない。文楽の根幹である浄瑠璃(本)に基づいた人物の解釈を中心に、その人形はどういう人物なのか、なぜその演技をするのかを常に自分に問いかけ続けるというものだ。
この本には、その問いかけによる深い考察と、納得できる演技を作り上げるための試行錯誤に支えられているかがつぶさに語られている。その解釈がかなり仔細で、文楽において「人形は義太夫の演奏に合わせて演技している」というのは基礎知識中の基礎知識だけど、「ここまで考えてやっているんだ」という素直な驚きがあった。現代演劇ならともかく、古典芸能にここまでの理知性を持ち込んでいることに、とても驚いた。
■
本の解釈を重視することは、実際の舞台にどう反映されるのか。
浄瑠璃の解釈と人形の演技を一致させた代表的な例は、玉男師匠が伝承演技を改定した例だろう。玉男師匠は若い頃から浄瑠璃の内容と演技の一致についてよく考えていたようで、自身が大役を任されるようになったとき、かねてから「おかしいのでは?」「人形をもっと美しくor的確に見せられるのでは?」と思っていた箇所の演技・演出を改定している。
中でも有名なのが、『一谷嫰軍記』熊谷陣屋の段、帰宅した熊谷に刀を携えた藤の局が襲いかかる場面だろう。我が子・敦盛を熊谷に殺害されたと思い込んだ藤の局は、熊谷の留守中に陣屋へ入り込み、熊谷の妻・相模を説いて邸内で待ち伏せする。熊谷が帰宅したところで隙を狙って陰から襲いかかるが、気づいた熊谷に刀を奪われ、取り押さえられる。ここは、浄瑠璃では以下のように語られる。
無官の太夫敦盛の首取たりと咄しに扨はと驚く相模。後に聞居る御台所我子の敵と有あふ刀。熊谷やらぬと抜所鐺摑んで。ヤア敵呼ばはり何やつと引き寄するを女房取付。ア丶コレ/\聊爾なされな。あなたは藤のお局様と。聞て直実恟りし。
この場面の人形の演技について、玉男師匠は以下のように語っている。
本公演での熊谷は、昭和四十四年五月の国立劇場が最初です。相模は紋十郎さん、弥陀六は勘十郎君、藤の局は簑助君でした。この時、かねがね疑問に思っていた演技を改めています。「熊谷やらぬと抜くところ」で藤の局が、熊谷の太刀を取って詰め寄る場面、それまでは藤の局が右手で刀を持って、トンと突き、熊谷に差し出すようにしていました。浄瑠璃には「抜く」とあるのに、右手で鞘を掴んでいては、刀を抜けないし、それどころか、逆に熊谷に向かって抜いてくれと言わんばかりになってしまう。その後の「鐺つかんで」でも、従来のやり方だと、熊谷役の左遣いが、鐺(鞘尻)を逆手に持って一回転させなくてはならない。この時、わざわざ鐺を掴むのも不自然です。普通なら藤の局の握っているすぐ下を持つはずでしょう。昔のやり方だと熊谷役には確かに便利なのですが、やはり理屈に合いません。
そこで、藤の局が右手で刀を取り、左手に持ち替えて抜きかけようとするところで、熊谷が局の裾を払い、前のめりになった拍子に、跳ね上がった鐺を背後から掴むように演出を変えました。膝を払う時、煙管でとも思ったのですけど、相手は女性ですし、手ですることに。いずれにしても、これで、局の体勢が崩れ、鞘尻が上がる。そうすると、一気に全てが解決します。左を遣うている間からずっと、そうしてみたいと考えていて、実は、昭和三十九年に藤の局の役がついた時(十月芸術座)、熊谷役の玉助さんに進言してみた。けれども、昔からのやり方のままでいくとのことで、主張を通したのは、自分が本役で熊谷を持つようになってからでした。
この改訂は定着し、現在の上演においても「藤の局が刀を右手から左手に持ち替えて熊谷にそっと近づく→気づいた熊谷が咄嗟に藤の局の膝を払う→藤の局が前のめりに転倒→反動で刀の鐺がはね上がる→熊谷が鐺をキャッチして、そのまま刀の鞘で倒れた藤の局の背面を抑えつける」という演技が踏襲されている。
古典芸能でも演出の変更って可能なんだと驚くと同時に、それが出演者の好みや自己顕示、「現代的にするために」新奇性を狙ってみたいとかではなく、浄瑠璃に紐付いているべきであるという考え方に端を発しているのがさらに驚き。一概に「昔の通り」がベストなのではなく、上演の中で常に検討が繰り返されているんですね。
■
ところでこの変更、文章で読むと、「なるほどぉーそりゃーそうですねぇー直して当然ですねぇー」と、100人中100人が思うだろう。ものすごく筋が通った、明快な理論なので。
ところが、実際の舞台でこの演技をこなすのは、実は相当難しいのではないか思う。人形は義太夫の演奏に合わせて演技をしているので、義太夫が「我子の敵と有あふ刀。熊谷やらぬと抜所鐺摑んで。」と演奏しているあいだに全ての手順を完了させないといけない。この部分、意外と一瞬で流れていってしまう。それにもかかわらず、演技の組み立てが非常に理論的なので、正確に手順を踏んだ演技をしないと、2人が何をやっているのか、観客に全然伝わらない。
人間なら自然にできる動作でも、3人で遣っている人形だと大変だ。熊谷役の3人、藤の局役の3人の息が相当合っていないと、こんな複雑な手順を踏んでの演技はまずできない。かつては藤の局が熊谷に刀を差し出していた訳もなんとなくわかる。たとえ話の筋として不自然でも、過去の演技のほうが舞台の取り回しがスムーズで、失敗が少ないのだろう。
舞台での実践を観てみると、演技を改定しようと玉男師匠が考え、共演者がそれに同意して協力したことのすごさがよくわかる。昨年12月東京公演の『一谷嫰軍記』熊谷陣屋の段の上演を見たとき、実際の舞台での理屈以上の難しさを感じ、玉男師匠の執念を知った。思いつきレベルでは絶対にできないし、まず周囲の人を説得できない。玉男師匠は苦労話を一切しないので、大変だったとかそういうことは1文字も書かれていない。この本で語られていることのすごさは、実際の舞台を観ることにより、より一層実感できるようになる。それも、この本の大きな魅力だ。
■
浄瑠璃に沿ってやればいいと聞くと、画一的になりそう、個性が不要なのかと感じる方もいるかもしれない。しかし、浄瑠璃が優位だからこそ、人形遣い個々の裁量は実はとても大きいと感じる。何をどこまでどう解釈するか、それをどう検討するかは人それぞれ。本書でも、ほかの人はどうやっているかの例が合わせて述べられている例が多い。
玉男師匠の深いこだわりは、周囲の人形遣いの談話からも窺える。玉男師匠の相手役を多く勤めた吉田簑助さんの話に、1,100回以上演じた『曾根崎心中』の徳兵衛でさえ、舞台に立つごとに、お初役の簑助さんへ、ああしよう、こうしようと声をかけていたというものがあった。また、一番弟子である当代の吉田玉男さんも、師匠の思い出として、玉男師匠は何回も演じている演目であってもいつも床本を読んでいたと話されていた。高い理知性と納得いくまでやるこだわりは、玉男師匠の大きな個性だったのだと思う。
■
かつての文楽は、こんなに理論的だったわけではないと思う。玉男師匠自身が過去と現在の違いに対してどう考えていたかは、この本では語られていない。しかし、別の学術調査用のインタビューを読むと、かつての人形遣いは細かいことは気にせず、型は決めていても肚はあまりない遣い方をしていた、その人物の心境なんかは見ていてもわからないと話している。これらの、自分のやりやすいようにして目立つ手法を玉男師匠は「昔の人形芝居の遣い方」と語っている。
このようなスタンスは、本書で語られている玉男師匠の理論とは真逆のものに思える。玉男師匠は、意識的に「昔の人形芝居の遣い方」から決別しようとしていたのではないか。映像で観ると、玉男師匠の若かった頃の演技もまた後年に比べれば大雑把に見えるので、技術の向上以上に、ある時期以降、考えてのことがあったのではないか。そのあたりの心境は、本書では語られていない。
■
ただ、古い時代の人形遣いがみな「昔の人形芝居の遣い方」だったわけではない。
演技の理論性に加え、本書のもうひとつの魅力となっているのが、玉男師匠の修行時代の思い出。明治から昭和にかけて活躍した往年の芸人たちや、当時の文楽座の様子が様々に語られる。玉男師匠は文楽に縁故のある家庭の生まれではなく、一般家庭から入門した人。入門時は当時の人形頭取であった吉田玉次郎の弟子になったが、本書で頻繁に名を挙げられるのは、初代吉田栄三(1872-1892)だ。この本を読んでいくと、玉男師匠が初代吉田栄三から大きな影響を受けていることがわかる。
例えば、『摂州合邦辻』合邦庵室の段。玉手御前が継子・俊徳丸への道ならぬ恋心を父・合邦に打ち明け、恋の取りなしをして欲しいと頼む場面。ここで重要な役割を果たす合邦の人物描写について、こう語っている。
栄三師匠を学んで取り入れさせていただいたのは、玉手がなおも俊徳丸と夫婦になりたいとわがまま勝手を言うのを聞いた合邦が、「まだ『俊徳様と女夫になりたい、親の慈悲に尋ねてくれ』とは、ど、ど、どの頬げたでぬかした」と、驚き呆れる場面。以前は合邦が玉手の台詞を鸚鵡に言うところで、眉を動かし、科を作るようにして色気を出し、ちょっとチャリめいて演じる人が多かった。それを栄三師匠は、合邦はそういう人物ではないと判断され、左右の方に向かって右手でトンと床を打つ、毅然とした態度に改められたのです。首(かしら)の性格からいっても当然そうであるべきで、私もそのまま踏襲させてもらっています。
ほかにも、若い頃の玉男師匠が初代栄三の遣う『一谷嫰軍記』熊谷の足をやりたくて、連日舞台の袖でじっ……❤️っと見つめてアピールし、ついにやらせてもらえた話や、栄三師匠の『義経千本桜』権太や『加賀見山旧錦絵』の尾上の足についたときにはみっちり絞られ指導された思い出が語られている。初代栄三は戦後まもなく亡くなったため、玉男師匠が間近で見ていた期間が長かったわけではないが(玉男師匠は戦時中、2度兵役につき文楽を一時的に離れている)、後年、様々な役がつくようになったとき、栄三師匠が遣っているのを一度も見たことがない役であっても、栄三師匠ならこうも遣われるだろうと想像し勤めることもあったという。本書全編を通して、初代栄三は玉男師匠の相当の憧れだったのだろうなということがしみじみと感じられる。
栄三師匠とともに頻繁に名前が挙げられるのは、女方の名人として有名な吉田文五郎(1869-1962)。相手役を勤めたときの自然な愛らしさが絶賛されているほか、文五郎師匠が実に理知的に浄瑠璃や舞台効果を解釈していたことが語られている。意外なことに、玉男師匠の『義経千本桜』大物浦の段の知盛は、文五郎師匠から指導を受けたものだという。また、同じ「検非違使(文楽では“けんびし”と読む)」のかしらを用いる『鳴響安宅新関』勧進帳の段の冨樫も文五郎写しだと言い、文五郎師匠の検非違使のかしらに似合うピリピリとしたシャープな品格を語っている。文五郎師匠の理知性は弟子だった吉田文雀さんの談話にも多く語られており、文雀師匠、ひいてはその弟子である吉田和生さんにも引き継がれていることだと思う。
玉男師匠は、初代吉田栄三と吉田文五郎が様々な整理を行い、人形の芸の近代化をはかったと語る。玉男師匠もその流れの中にある人だろう。
■
理論的な浄瑠璃の読み解きに加えてもうひとつ、本書で印象的なのが、頻繁に出てくる「品」という言葉。
人形は、浄瑠璃に描写される性根やかしら(人形の顔のタイプ)に見合った品を踏まえることが重要だという考えが感じられる。現代の日常生活では「品」という概念すら存在していないが(?)、文楽の時代物は身分制度がある時代、公家、武家など身分の高い登場人物はそれに見合った描写が不可欠だ。
玉男師匠の品格高い芸風を代表する役としては『菅原伝授手習鑑』の菅丞相が有名だ。玉男師匠は、菅丞相の役を「立役人形遣いが勤める役の中でも最も位の重いもの」と語る。
それはさておき、本物の丞相で一番大切なのは品格の描写です。公卿としての、また高い教養の持ち主としての人物像を、少ない動きの中に滲ませていく。『忠臣蔵』の大星由良助も孔明の首ですけど、それ以上に細かい神経を使うので、芯の疲れる役ですね。
首はこの丞相に最も上質の物を用います。これも以前は、殿上眉といって実際の眉毛の上に丸く印を施していたことがありましたけど、今は単に“べらぼう眉”と呼ばれる描き眉にしている。お公家さんらしさを出そうとしたのだと思いますが、ちょっと滑稽でもあるでしょ。殿上眉のない方が品はある。
官位をもつ学者である菅丞相では上記のような考えになるが、公家に化けた武家という特殊な役、『奥州安達原』環の宮明御殿の安倍貞任になるとかしらが文七になるので、これまた難しい。
“矢の根”の貞任は、桂中納言則氏に化けていて、衣装は衣冠束帯のお公家さんの姿です。ここは、あくまで肚を割らず、公卿らしい品格を滲ませるのが大切です。とはいえ、首が『菅原伝授手習鑑』の菅丞相のような孔明ではなく文七なので、よけいに難しい。(略)
(略 切場“袖萩祭文”で)貞任は切腹した傔杖の懐から密書を抜き取ります。ここで、ずっと以前は、貞任の人形が「してやったり」とでもいう風に「べー」と舌を出す演技をすることがあったそうです。私は話に聞いているだけで見たことはありませんし、栄三師匠ももちろんそんなことはなさっていません。素朴な面白さはあるでしょうけど、貞任の性根にはやはりふさわしくない。
立役(男性の役)の場合、かしらの種類が多彩にあるためか、かしらが何であるかもその役の人物造形に関わってきて、それゆえの難易度が発生することがよくわかる。
■
加えて玉男師匠は、人物描写はわざとらしく拵えたものではなく、内面から滲み出ることが重要と考えておられたようだ。特に色気に関しては描写が慎重。『本朝廿四孝』十種香の段に登場する武田信玄の嫡子、超キラキラ系イケメンの武田勝頼の描写をこう語る。
とはいえ、勝頼の色気はあまり意識しては表現しません。また、計算して出せるものでもない。さりげなく滲み出るようでなければいけません。文五郎師匠の八重垣姫も、得も言われぬ可愛らしさでしたけれど、拵えたものではなく、あくまで自然な描写でした。(略)勝頼の場合は衣裳が美麗なので、それだけで十分華やかですし、あとはやはり首の遣いようです。歌舞伎の二枚目のように、襟を衣紋に抜いたりしない。本来、私はどんな役でも、棒襟をきっちりとつけるのが好みです。
対して、これまた玉男師匠が得意としていた世話物の二枚目の色気はどう表現するのか。『心中天網島』の主人公、治兵衛について問われた玉男師匠はこう語る。
和事の二枚目の色気をどうやって出すか、ですか。拵えた色気はいやらしいものですし、自然と滲み出ないといけないのですけど、技術的にはまず胴串の握り方ですね。普通、立役でも時代物なら力強さを出すために、左の掌の中心部に胴串をどっしり据えて、五本の指でしっかり握る。対して女形は指の付け根あたりに胴串をふんわり置く感じで、握り方も柔らかい。二枚目はその中間くらいでしょうか。ただ、おなじ源太の首を用いても、裃をつけた『本朝廿四孝』「十種香」の武田勝頼や『絵本太功記』の武智十次郎と、世話物の治兵衛や忠兵衛のような役はまた違う。そのあたりは微妙で、言葉では曰く言い難いのですが、時代物の方が色気の描写を控えめにする必要があります。
この談話はかなり具体的で、かつ、客席からは絶対に知りえない「胴串(人形のかしらの下部についた棒。主遣いはここを左手で握る)の握り方」というヒミツ(?)が語られているのも貴重だ。
玉男師匠の「おさえた中の的確な表現」へのこだわりを読むと、みんなおなじように見えていたいまの人形遣いさんにもそれぞれの考えや遣い方があることが浮き上がってくる。過剰めの演技をする人がなぜそうしているのか、地味に思える人は本当にただ地味なのかを考えるきっかけになる。
■
舞台のちょっとした裏話が散りばめられているのも楽しい。客席から見ていると、舞台上にはたくさんのお人形さんたちがうぞうぞしていて、衣装をもぞもぞ脱いだり、中空からモノをぱっと突然取り出したり、エア椅子にどっしり腰掛けていたりする。そういった舞台は、いったいどういう段取りで進行しているのか。
例えば、物語上重要な小道具の準備。『加賀見山旧錦絵』長局の段で、尾上が自害する前、文箱を開けていくつかの中身を取り出る場面がある。玉男師匠は後年の立役のイメージが強いが、尾上などの品格の高い立女方も多く勤めている。この尾上役のときは、箱の中身に入れ忘れのないよう、初日からしばらくは準備してもらったものを自分でも確認していたそうだ。
そして、遣っている本人しか気付けない、人形自体からくる難易度。たとえば、『一谷嫰軍記』熊谷陣屋の段の最後に登場する源義経。首実検の最中、舞台の上手にじーーーーーーーーっと座っているだけなのでラクそうと思いきや、鎧をつけているせいで重量があり、ふらふらさせずに綺麗な姿勢で持っているのが大変なのだという。上演中は観客みんな熊谷を注視しているので、義経はいるような、いないようなイメージ(失礼)だったけど、大変だったんですね。
ほかにも、『良弁杉由来』二月堂の段の良弁上人、『桂川連理柵』帯屋の段の長右衛門など、じっとしていて動きの少ない役の難しさ、それゆえのやりがいは繰り返し語られている。じっとしている系の役の重要さは、ぜひ本書を読んで確かめていただきたい。当代の玉男さんがなぜあんなにもじっとしているのか、わかった気がした(?)。
誰も気にしていない(褒めてます)左遣いや足遣いの、見えない見所(?)の披露も。『源平布引滝』の斉藤実盛など、舞台上で馬に飛び乗る人形を綺麗に馬に乗せるには、足遣いと間合いを合わせることが必要だとか、『絵本太功記』で武智光秀が遠寄せの太鼓の音を聞いて下手へ向かって駆け出す際の「団七走り」では、左遣いが人形の前に回って主遣いの腰を支えながら人形を遣うので、その加減が重要であるとか、3人遣いの文楽ならではの左遣い・足遣いとの関係性の話題も興味深い。このような話を読んでいると、普段、存在感の薄い(褒めてます)左遣いや足遣いの動きがいかに重要か、具体性を帯びてきて、よくわかる。
■
玉男師匠の言葉は常に明晰な言葉で語られているので、玉男師匠の舞台を観たことのない、現在の文楽の観客である私にも何を言っているのかが理解できる。これって、すごいことだと思う。芸談本には、自分の意見と他人の意見を混同している方とか、本心を明かさずものすごくおおざっぱな一般論を語る方とか、独自の精神論を語る方も多いので……。本書の明瞭さ、仔細でありながら読みやすい文章は稀有なものだ。おそらく、取りまとめをされた森西真弓さんの工夫によるところも大きいだろう。私は玉男師匠の実際の舞台を観ることはできなかったけど、この本を通して、玉男師匠が文楽に残した偉大な足跡を知ることができた。
談話のテーマになっている演目は以下の通り。
伊賀越道中双六/一谷嫰軍記/妹背山婦女庭訓/絵本太功記/奥州安達原/近江源氏先陣館・鎌倉三代記/加賀見山旧錦絵/桂川連理柵/仮名手本忠臣蔵/源平布引滝/恋女房染分手綱/心中天網島/心中宵庚申/菅原伝授手習鑑/摂州合邦辻/曾根崎心中/染模様妹背門松/玉藻前曦/壇浦兜軍記/夏祭浪花鑑/鳴響安宅新関(勧進帳)/彦山権現誓助剣/ひらかな盛衰記/双蝶々曲輪日記/平家女護島/本朝廿四孝/嬢景清八嶋日記/冥途の飛脚/伽羅先代萩/義経千本桜/良弁杉由来
各演目の解説のほか、本文中に出てくる文楽専門用語や人名をまとめた用語集つき。このあたりは下手な入門書よりわかりやすく書かれており、これだけでも価値あり。
談話の内容があまりに詳細なので、観たことのない演目のページは読んでいても何言うてるか本当にわからない。公演に通ううち、「読める」ページが増えていくことが楽しい。文楽を観るようになって4年、もうほとんどのページを読んでしまったけど、まだ読んでいない数演目を読み終わる日が楽しみ。
……と、いろいろ理屈を並べたが、玉男師匠についてなにより本当に一番びっくらこくのは、人形遣いとしてのぶっちぎった技芸のレベルの高さだね。記録映像で観ると、演技が理論的とかそれ以前に、とにかく、もう、めちゃくちゃにうまい。衝撃的。本当に次元が違っていて「は???????」となる。NHKが往年の名演をまとめた文楽DVDをたくさん発売しており、人形の重要な役は大抵玉男師匠なので、本書を手にされた暁には合わせて実演も確認してみてください。
■
備考
前述の通り、本書は国立劇場・国立文楽劇場の売店でのみ店頭販売されているが、国立劇場売店の文化堂(http://bunkadou1.com/)から通信販売で購入することもできる。本体価格1,000円、送料200円。
通販ページ https://store.shopping.yahoo.co.jp/bunkadou/1-580.html
■
文楽《再》入門 ブックガイド 過去記事
第一弾