ちいかわが文楽化したら……その3 後編です。








今年の大阪鑑賞教室はAプロだけ見た。

◾️
二人三番叟。
久しぶりに「二人組」らしい三番叟を見た。いつも人形の振りが合っておらず、タイミー発注で偶然やってきた人同士状態になっているが(失礼)、曲に対する間合いの取り方、ペアになる演技のタイミングが一致していた。芸の系統が同じだからだと思うが、まるで先輩後輩二人組のようだった(本当に先輩後輩だぎゃ)。飛行機で出張へ行くので羽田空港にやってきたはいいものの、いつまで経っても自分が乗る便の手荷物検査がはじまらないので混んでるのかなぁと思っていたら、「せ、先輩ッ…! これよく見たら成田発って書いてありますッ…!」だったことが出発17分前に発覚し大慌てしているようで、良かった。
一番評価したいのは、間合いが合っていること。ちゃんと曲に合わせて踊っている。これだけ頻繁に出ている演目でも、曲に合わせて踊れない人、たくさんいる。当たり前のことだけど、人形は曲に合わせて踊って欲しいし、曲に合わせて踊っている三番叟は気持ちいい。『二人三番叟』はこうであって欲しいと思う。
三番叟で難しいのは、いかにかしらをまっすぐ遣えるかだろう。三番叟は帽子をかぶっているため、顔の正中線がわかりやすい。「初日は〜」のところで、顔をコクコクと振る振付があるが、単に頭をうなずかせるだけではなく、上半身ごと直下へ下げなくてはいけない。みんながみんな本当にまっすぐ下げられるかというと、難しい。玉路さんの三番叟役ははじめて見たが、かしらをヨレさせずにしっかりと首を座らせて遣っており、上手いなと思った。しかし、かしらを左右に振るとき、上手側はしっかり振り向けているのに、下手側にちゃんと向けていないのが惜しい。単なる正面向きになっている。かしらを連続して左右にきっちり振るというのはかなり難しいようで、曖昧になっている人が多い。なんなら、玉男さんも出来ていないことがある。でも、検非違使のかしらは、本当にしっかり振らんといかん。まだお若いので、頑張ってお稽古してくりゃれ。と思った。その点、おにいさんの玉翔さんは均等に左右へ振っていて、さすが初代玉男の弟子、師匠をよく見ていたんだなと思った。
三味線は良かった。曲の構造を理解し、舞台全体を牽引する演奏になっていた。常にこうでいて欲しい。しかし、ここまで自信をもって弾けるようになるまでに時間がかかるのだろうと思う。やはり最後は自分との勝負か。
『二人三番叟』は、頻繁に上演される「こればっかりかい」な演目。だけどその分、出演者の技量がはっきりとわかる。そういう意味では、客としてもとても勉強になる演目。と思った。
◾️
解説。
今年は妙に解説の時間が長くとってあるなと思ったら、通常の解説のほか、来場者に人形遣い体験をしてもらうパートが設けられていた。
私が見た回に、「場内半分以上男子中学生」という、技芸員さんにとっては夢のような回があった。男子中学生たちは体験者に指名してもらおうとキャアキャア騒いでいた。元気やのー、ええのー。技芸員さんも、いつになく丁寧に指導していた。おまえら、これまで「手を叩くときはかしらをちょっとうつむかせてください☺️」とか「左手のほうを高くしてください❤️」とかまで言うてへんかったやろ。指名された少年たちはなかなかうまかった。主遣いの子は人形がちゃんと前を見るように遣っていて、本当に立派。簑太郎さんは「ゾンビみたいですね〜⭐️」と言っていたが、「本職」かてガラクタの百鬼夜行になっとることしょっちゅうあるやろがい。と思った。
簑太郎さんは、終了後に体験の感想を語った生徒さんから「名人」と言われて嬉しそうにしていたのが良かった。
演目解説で、「恩のある人のために自分の子供の命を差し出すという現代では考えられない話ですが」と言っている。しかし、それは逆だよね。江戸時代でもそんなこと考えられないから、芝居になっている。突飛な話じゃないと商売にならない。
この物語のポイントは、松王丸が忠義のために子供の命を差し出すことでなく、こんな極論に走らざるを得ない理不尽な境遇に追い詰められたことだ。鑑賞教室の解説は基本的に制作が作成した台本だと思う。こんな説明でいいと思っているというのはどうなのだろう。解説では、江戸時代の「差別(区別の意)」と現代の「差別」を混同している人、前近代の「戦(いくさ)」と近代戦を混同している人もいるが、なんでそんなこと言うんだろと思う。わざわざ安直で誤りのある理解に誘導する必要、あるのだろうか。
◾️
菅原伝授手習鑑、寺入りの段、寺子屋の段。
松王丸・玉志さん、千代・清十郎さんが良かった。清廉で透明感がある寺子屋になっていた。
いままで玉志さんの松王丸を何度か見てきたが、ご本人の性質にバチハマりする役ではないためか、これまでは試行錯誤があるように感じていた。が、ここで自分の性質をいかした方向に落ち着いたのか。過去に玉志さんが「車曳」「佐田村」の松王丸に配役されていたことがあるが、そのときの松王丸と性根が繋がっている。派手な演目としての虚飾は行わず、ひとりの青年としての、等身大の松王丸になっていた。『菅原』の全段からすると、これが、「寺子屋」が独立して上演されるようになる前の、本来の松王丸に相応しい人物像なのだと思う。
人物像としては、やはり、かなり若く見えていた。動きがしゃきしゃきしていて、凛々しい雰囲気になっているからだと思う。
玉志さんは、「どのような演技をするか、どのタイミングで演技をするか」は基本的に玉男さんと一致している。しかし、演技は同じでも、役の雰囲気は、全然違う。玉志さんは、若さゆえの生真面目さが強く出て、松王丸の心情が客の眼前ギリギリのキワまで迫っている。心に前のめりさがあるのだ。とても一生懸命で、本来は「嘘をついている」はずの前半ですら、すでにとても哀しそう。しかし、玉男さんの松王丸にはもっと大きな余白がある。松王丸と客のあいだには、エアバッグのような巨大な空気のクッションが挟まっている。観客は、クッションに阻まれて、松王丸の本当の心情を知ることはできない。そういう意味では、玉男さんの松王丸は、不気味に見えて、抒情的でもある。
松王丸は「大きい役」という理解にとどまる人も多い中、方向性は違えど内面性をもって演じられるというのは、すごいことだと思う。
ほか、過去に玉志さんが松王丸に配役されたときから、明らかに改善されているところがあった。これまでは、最初に「ヤレお待ちなされ」で駕籠から降りたあと、過剰な「仮病」演技をしすぎて、単にまっすぐ立てていないだけに見えていた。しかし、今回は玉志通常営業的に、しゃきっ!と立っていた。咳き込みも控えめ(床も控えめだからだが)。このほうが良い。また、衣装の捌きがかなり綺麗になっており、通常の武士の役同様のスムーズな処理になっていた。役に慣れたんだなと思った。
逆に、これまでと変わらないのは、二度目の出の野袴姿でのパートと、いろは送りのパートが首実検よりも上手い点。後半のほうが松王丸の性根そのもので演じられるからだろうか。小太郎の遺骸を乗せた駕籠の扉を閉める手つき、千代とともに踊る際に泣き崩れる千代に添えてやる手元も、やはり、とても良い。瑞々しい健気さと情緒があり、松王丸の繊細な優しさが出ていた。これは本当、玉志さんならではの人物像。あの優しさは、どこから来ているのだろう。
それにしても、玉志さんと清十郎さんの透明感は本当にすごい。文楽の場合、人形配役にかかわらず人形のかしらは基本的に同じ。なので、透明感のあるなしはルックスではなく、配役された人形遣いの性質から生まれているということになる。生身の人間の世界では、「透明感」というとメイクや服装での小細工が喧伝されるが、所作や姿勢だけでここまでの透明感が出るんだなと思った。透明感を出すべく青のコンシーラー(ジバンシイ プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター ブルー 税込¥5,060)を目の下とデコにぬーりぬりして「あ、なんかこれ見たことある!『四谷怪談』で戸板がひっくり返ったときに裏側にくっついてる、お岩さんじゃないほうの人だよね?」状態になってる場合ではない。この多大な透明感は常に姿勢を正し、立ち上がる時にはまっすぐに立ち上がる、丁寧な所作を心掛け指先の細かい動きにも気を配る等によるものだと思う。今後の人生の参考にさせていただきます。
今回は、芝居のきっかけを作ることができる人の重要性をつくづくと感じた。
今回、源蔵・戸浪がかなり不慣れな人に配役されていた。本人なりに頑張ってるんですというのは理解できるが、なかなか大変なことになっていた。自分がわかる範囲の振付をやること自体が目的化しすぎて、動きのタイミングが義太夫演奏に合っていない。思い出し次第やっている状態。人形の動きが義太夫から離れてしまうのは、文楽ではかなり難のある状態だ。また、文章に対する心情表現のメリハリが不自然だったり、演技が飛ぶなどの事象が発生していた。今回は床も不慣れなため、一層よくわからない状況。源蔵戻りのあと、源蔵と戸浪がふたりで会話するところは「寺子屋」でも最も難しい部分だが、かなりガタガタになってしまっていた。
しかし、松王丸が出ると、全体的に演技がしっかりする。それは、玉志さんの演技のタイミングやメリハリがしっかりしているからだと思う。玉志さん自身も、松王丸という役に習熟しているわけではない。しかし、演奏に対する適切なタイミングで演技ができているので、源蔵・戸浪もそれにリアクションすれば、自動的に演技タイミングが正しくなる。また、演技の強弱も適切についているので、それに合わせて芝居すれば、強弱がつけられるようになる。あるいは、相手役の演技が飛んでしまったとしても、リアクション演技をすることで「あ、自分演技飛んじゃった」と気づくだろう。
具体的に言えば、戸浪は、芝居が義太夫に乗っておらず、テンポがすべて緩慢になっている中、机の数を数えた松王丸に凄まれるところで松王丸が適切なタイミングでキッと強く睨むことによって、それを受ける戸浪も自動的にタイミングがあうし、松王丸に呼応する芝居として強い反応が出ていた。この調子で、ほかの部分でもメリハリ付けの必要性をわかってくれるといいんだけど。
あるいは、首実検の直前のくだり、松王丸が首桶を受け取ろうとするところで、源蔵が松王丸を改めて睨む演技をする必要があるのだが、ある日の上演では、飛んでしまっていた。しかし、松王丸は通常通り、驚く演技をしていた。これ、客席から見たら、松王丸が意味もなくビビっているように見えて、かなりの違和感がある。それでもあえてリアクション演技をしていたことで、源蔵役は自分の演技が飛んだことに気づいたと思う。実際、翌日は、演技が飛ぶことなく、源蔵も睨みをきかせていた。
周囲をリードするような演技の振り出しができる人の存在は、本当に、重要。不慣れな人が多い場合、こういう人が一人は舞台に出ていないと、意味不明になる。和生さんがよくやってるよね。お母さん役のとき、子役の若手がまごついてたら、世話をする振りをしながら、本当のお母さんのように「立たせる」「座らせる」「こっち向かせる」等の演技の示唆をすることがある。立つタイミングで手を握ってあげるとか。そうしてもらうと直感的にわかるし、若い人たちも「ここではこうすればいいんだ」と勉強するわけだよね。演技を思い出すこと自体に必死にならず安心して舞台に立てるので、パフォーマンスも上がるし。文楽自体の今後にもいかされる、大切なことだと思う。
玉志さんは、普段から、たとえ相手役がぬぼ〜っとしてても、一人でリアクション演技をし続けていることが多い。それ自体は、この役はこうすべきだという自分のこだわりを貫いているのだと思う。それでも、トラブルなどによってやむを得えず演技を続行できない場合はパッと演技を抜くわけだから、やっぱり、相手役の人がリアクションしてくれる日を待ってるのかなとも思う。
ただこの演目、演技の振り出しをすべきは、本来は源蔵だろう。「寺子屋」の物語の軸は源蔵であり、彼の心情に沿って物語は展開している。源蔵が話をリードしないとわけがわからなくなる。今回の鑑賞教室では、源蔵役はすべての回で「チャレンジ配役」になっているが、がんばり中な人が松王丸をやる場合、しっかりした人が源蔵役をやったほうがいいと思った。ほかの配役がどうなっているのか、おそろしい。
菅秀才〈吉田玉征〉はあいかわらず巨大ハムスターのようだった。なんなんだその貫禄。師匠に似たということだろうか。後半、正装(?)に着替えてからの貫禄もドすごい。確かにある意味、菅秀才に合った芸風。
「寺入り」が終わったあと、「寺子屋」の冒頭で源蔵が出るまでのあいだ、舞台に出ているよだれくりや手習子たちが子供だけで遊ぶ演技を見せる。その際、よだれくりが菅秀才に食べ物(千代のお土産の野菜の煮付け)をおすそわけしようとする場合があるが、菅秀才は受け取らない。ところが、今回、菅秀才が食べ物を受け取っている回があった。さすがに食べてはいなかったが、受け取る菅秀才もおるんか!?!?!?!?食いしん坊!?!??!?!?!と思った。
よだれくりが隠し持っていた食べ物を菅秀才へ渡そうとする演技は、玉翔さんがよくやっていたよね。子供ならではの素直な優しさや気遣いの表現で、好ましい。玉翔さんの演技の源流が何なのかはわからないけど、いまの若手は結構みんな真似しているので、このまま定型化するかな。
しかし、今回のよだれくり〈吉田玉彦〉は、ほかの人と少し演技が違う。野菜をちょっとかじってから、菅秀才に渡そうとしていた。1個目を少しかじって微妙な顔をしてから一旦しまい、2個目を取り出してまた少しかじってウンとうなずいてから渡すという流れ。なぜ食べかけ?と思ったが、もしかして、毒味してるってこと? 玉彦よだれくりは以前から「かじる→渡そうとする」という演技だったとは思うが、そのときは普通の「おすそわけ」に見えていた。ただ、今回は結構慎重に味(?)を確認していた。よだれくりは菅秀才の正体を知っているわけではないが、師匠の息子=「お主」だと思っているとして演じているのかな。普段の玉彦さんを見ていると、話の流れを踏まえて演技をしているのかなと思う節があるので*1、千松(先代萩)的な演技を取り入れているのかもしれない、と思った。
よだれくりは「寺入り」冒頭のノンビリコとした緩慢な動きも良く、曲の雰囲気に合った演技が検討されているのを感じた。
三助〈吉田玉峻〉は、持ってきた文箱をふーふーして磨く演技で、ちゃんと「ふーふー」しているのが良かった。かしらと上体をうまく遣って、小ぶりな動きの中に、それが何を示すかを明確にしていた。居眠りは、寝る準備をシッッッッカリしすぎて、居眠りに見えないね。居眠りをする人形は難しい。若手はまず居眠りに見えない。客席の学校観劇の生徒さんたちがわざとらしく「居眠り」風のポーズをとっているのをよく見るが、あれと同じ。姿勢が不自然で、かつ急に寝るので、「ねむみ」ではなく「力み」を感じる。なお、私が観劇した回で、引率の先生に寝ている方がいたが、さすが先生は貫禄のマジ寝で、文楽劇場客席にはびこるプロフェッショナル・ツメ人形と寸分違わぬ寝方だった。若造よこれを真似せよ。
それにしても、手習子たちのお迎えパパジジツメ人形たち、公演によってどんなツメ人形を使うかが変わってるよね? 先頭のジジイはいつも同じだと思うけど、うしろのほうはなんか時々違う人がいる気がする。役を宛てられた人の好みなのか、取り回し都合があるのか? 芋チルは、このなすびボーイ、かわいい子など、かしら固定の子も多いと思うが。
あと、「南無阿弥陀仏」の六字の旗が新品になっていた(?)。
床は、三味線〈前=鶴澤燕三、後=野澤勝平〉が良かった。不安のある舞台に筋道をつけて、方向を指し示していた。
「寺子屋」は、配役される太夫の個性が出る演目だ。ある程度の水準の人までは、よくも悪くも「教科書的」な語りになる。古典芸能は型を押さえることが重要なので、自分が何をやっているのかわからない人にとっては教科書通りにやるのは重要だが、それだと、「寺子屋」とは一体誰の話なのかがわからない。
一定以上の人になると、「一体誰の話なのか」に語りの重点が置かれ、太夫の個性が出て、話の芯や輪郭が明確になる。近年では、2022年1月大阪公演で出た際に、錣さんが源蔵(+戸浪)中心の語りをしていたのは印象的だ。今回の「前」配役の藤太夫さんも同様で、源蔵を中心とした構成になっていた。源蔵の語りにおいては間合いが特殊になっており、こだわりが感じられた。源蔵役の人はかなり大変だったと思うが……。ただ、戸浪が喋り方が均一で、かなりペラッとしてしまっていた。均一すぎる人形の演技とあいまって、戸浪は謎の状態になっていた。そのほか、まだ詰めきれていないところがあり、人形さんたちもうまく読み取りきれないのか、松王丸の決めとそのツケ打ちが不思議なことになっている箇所があった。
人形に笑って遣っている若手がいる。二度出がある役で二回とも笑っているのは、論外。この人が笑っているのを見るのは今回が初めてではない。出遣いで客前に出る役を与える水準に達していない。以前にも述べたが、未熟なせいで下手なのは「おきばりや〜」と思えても、舞台上の態度が悪いのは本当に話にならない。ただただガッカリ。周囲は注意してあげるべきだと思う。
◾️
「文楽鑑賞教室」は初心者向けをうたう公演ながら、実は出演者のほうが初心者なのがヤバイ。本当にヤバイ。古典芸能の鑑賞だと、はじめてご覧になる方は「この舞台は素晴らしいものなんだ」「出演者はみんなすごく上手いんだ」と思い込んで、褒めるところを探さなきゃと思う傾向があるが(私もそう思っていた)、そうじゃないんですよね。なかなか難しい体制で、解説ではあえて「わたしたちもみなさんと一緒に学んでいます」と言ってもいいと思う。私も一緒に勉強させていただきます。
「寺子屋」は『菅原伝授手習鑑』四段目の切であり、ここに至る前提がわからないと、ストーリーがあまりに意味不明すぎる。初心者の方はまずどうやっても話を理解できないだろう。しかし、有名な演目だし、文楽の王道パターンを踏まえてた展開なので、これを見たという経験はのちのち有効ではある。
話を理解してもらう、共感してもらうという観点からすると、『伊賀越道中双六』の「沼津」が一番現代の鑑賞に耐えうる内容なのではないか。ただ、「沼津」の良さは、老親や年若い妹を心配する大人の主人公の心情という「大人向けの物語」が描かれているからこそだろう。私も若いころに見ていたら、「なんかそういう昔話?」にしか思えなかったと思う。文楽のよさを若いうちから感じてもらうのは、なかなか難しいね。
今回は、無料配布パンフレットが舞台写真満載なのが良かった。あらすじ紹介をする際、ただ文章を長々と書くのではなく、シーンを小分けにして、それぞれに舞台写真を添えてある。そうなんだよ、写真があると、帰ってからの思い出し度が段違いなんだよね。人形の顔の証明写真(?)入りの人物相関図とともに舞台写真があると、あとから「このシーンはこういうことだったんだ」という理解もしやすい。今後にもいかされて欲しい編集だと思った。
最近、いろいろと思うことがあり、結局、文楽は、「国語」ができないとどうしようもないと考えている。そこからだけは本当に逃れられない。客も出演者も。
■
モー

モー

モー
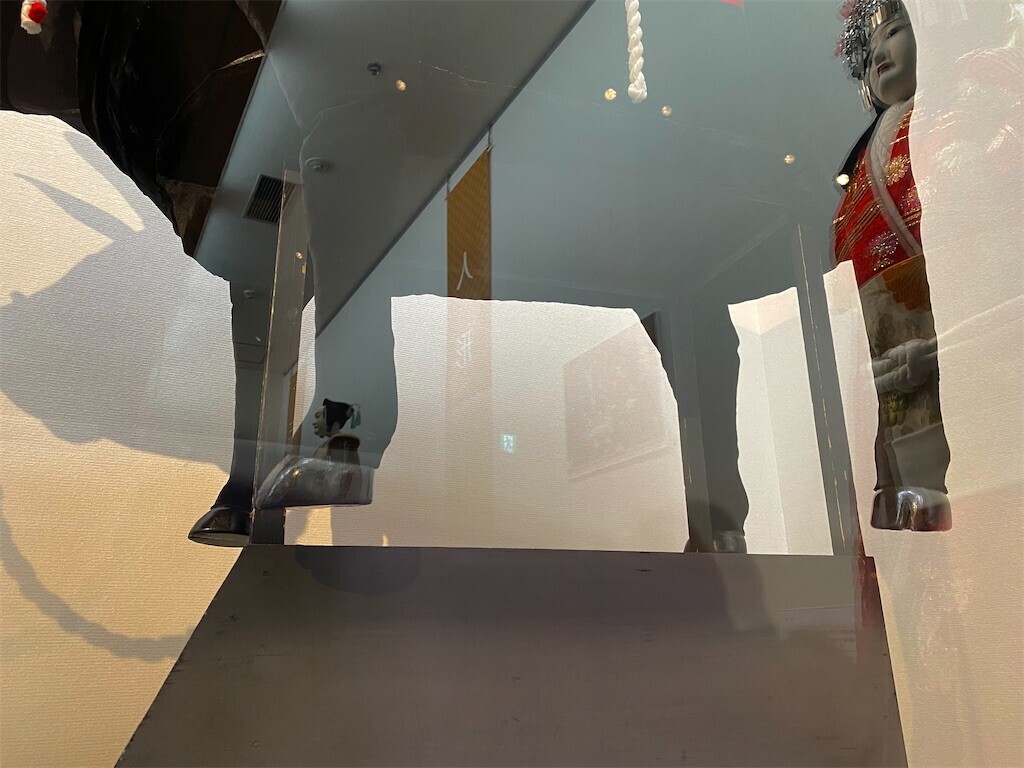
(わかりづらいですが、うしのおなかに穴があいていて、人が入れるようになっています)
◾️
鑑賞教室を観たあと、奈良へ行った。ふだん奈良に行くときは新幹線京都下車で行っていたが、難波からだと近鉄で35分ちょいで行けるのか。近い。

猿沢池。池のまわりに柵がなく、中学生が池へ手を突っ込んでいた。


しか。まるまると太っていた。観光客のみなさん、「しか!」「でか!」「ディアー!」しか言ってなくて面白かった。
しかさんたちはおなかいっぱいだったようで、しかせんおねだり等はされなかったが、特に意味もなくにおいを嗅いでくるのは、何。

二月堂としか。

東大寺の有料ゾーン、十数年ぶりに入った。東大寺周辺は観光客で混雑していたが、課金が必要な大仏殿は昔と同じくらいの人出。大仏さんのくそでかぶりにみなさん大盛り上がりしていた。穴くぐりに詰まっている人がいるのが良かった。
*1:5月東京公演の『ひらかな盛衰記』楊枝屋の段のおさる役、後半日程では、「おさるは最初から家主さんの行動を真似している」という演技をしていた。おさるは最後に家主さんとまったく同じ振り付けで踊るくだりがあるので、その伏線として演じていたのだと思う。ごちゃごちゃとした余計な動きをつけたくなるところだと思うし、前半日程では無駄な動きが多かったが、最後にはちゃんと意味のある「芝居」になっていて、良かった。