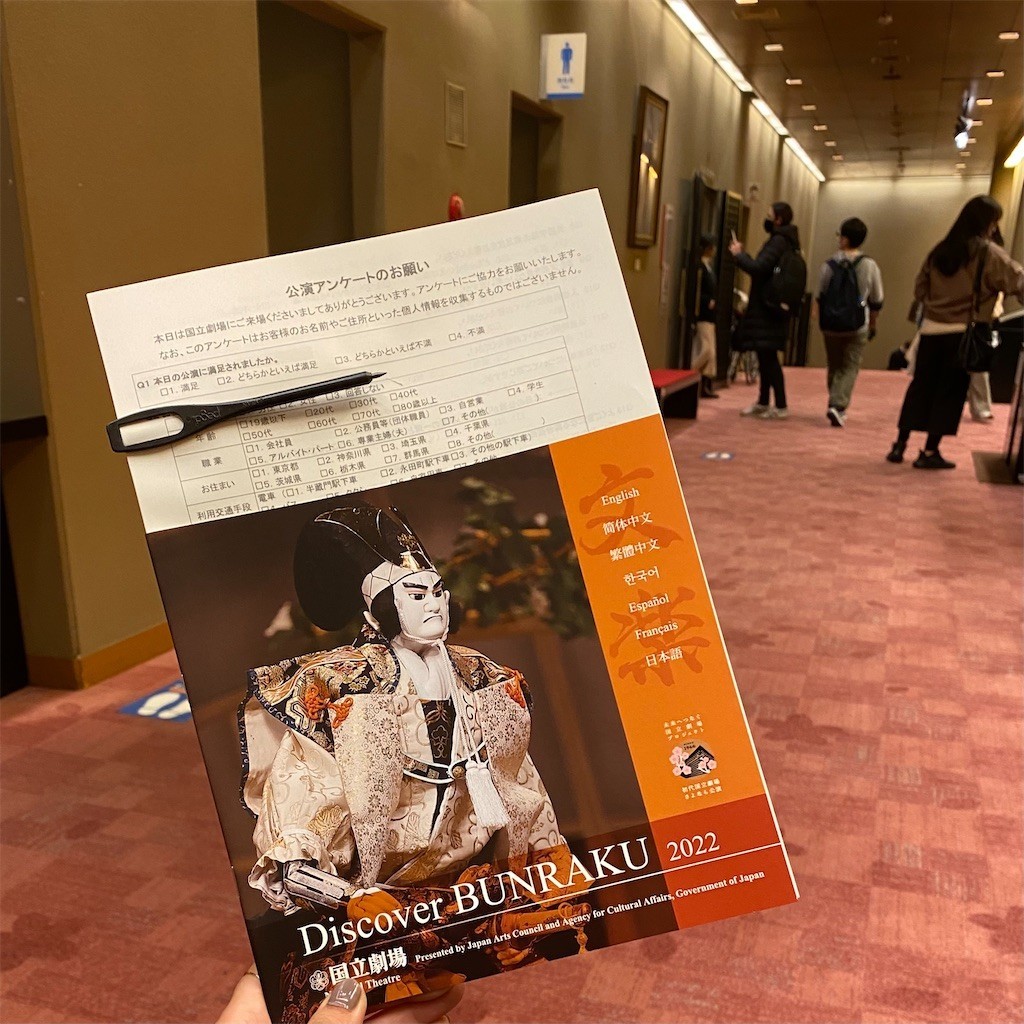今年の初春公演は、舞台が東大寺、吉野、新口と、奈良スペシャル。
新口村(現在は新口町)は観光スポットではないけれど、免許センターがあるので、奈良の人はみんな知っているそうです(以前、演目解説でヤスさん?が言っていた)。

■
第三部、傾城恋飛脚、新口村の段。
今月で一番良かった。
「新口村」は、いかにも芝居らしい、虚構の物語だ。登場人物はみな澄みきった心を持っていて、つねにお互いを思い合っている。こんな都合のいい美談、端から端までなにひとつありえない。この虚構を、実感をもった姿で観客に供するのは、実は、“リアル”というエクスキュース、言い換えれば、つまらなくても言い逃れができる近松原作(忠兵衛らが孫右衛門の目の前で捕まるパターン)よりも、難しいのではないだろうか。誰もが「こうでありたい」と思うような世界を、白けさせずに舞台へ定着させることのできる力が必要だ。
そのなかで、今回は、床といい、人形といい、いま「新口村」をやるうえでのベストメンバーだったと思う。
特によかったのは、孫右衛門の描写。
錣さん〈床=切〉と玉也さん〈人形=孫右衛門〉は、基本的には「やりすぎ」感の強い人だと思う。でも、こうして孫右衛門として組み合わせて舞台を見てみると、むしろ自然。情に折れてしまう田舎の普通のお爺さん像に、ジンとくる。二人とも装飾過剰なようでいて、合わされば実は余計な塗り込みなんてなかったんだと思わされた。
錣さんはあの過剰さ、異様なまでの情の深さがいい。
孫右衛門は、「孫右衛門は老足の……」と出てきた瞬間、「ング…ング…」と唸っていた。「老衰ッ!!!」感がすごい。これ別に錣さん自身がまじで唸っているわけではなく、人形も一瞬立ち止まるので、合意の上でやっている表現だと思う。孫右衛門はそこまで老いぼれてねえだろと思うんですけど、でも、「おじいさん」って、遠くから見ていると、直に接しているときより、だいぶ衰えて見えませんか? ちょっと寂しそうな感じがしたり、疲れている感じがして、私と話してるときはこちらを心配させないように頑張って元気なように振舞ってくれてたんだなと思わされるというか……。孫右衛門も、梅川に助けられたあとは「もう大丈夫」ばかり言って、しっかりした喋り方になる。そういう意味での、老親のリアルさがあると思った。
梅川も、とても毛深そうで、良かった。清十郎さんの梅川はまったく毛深そうじゃないのに、喋り方だけびっしりしっとりと毛深そうなのが、かなり良い。情が濃い女すぎる。
錣さんの「新口村」は以前にも聴いたことがあるけど、今回はぐっと良かった。素朴で普遍的な話を、それそのままに素朴に普遍的に表現することで舞台をシッカリと成立させる才気のある人だと思った。
清十郎さんには梅川がよく似合う。
梅川のまごころがそのままに表現されていた。梅川は、設定や言動だけ抽出してみれば、現代の感性からすると相当鼻につく役だと思う。それをそうと思わせないのは、人形浄瑠璃の力、清十郎さんの力だなと思う。
クドキはひとりで舞い踊っているようで、その先に忠兵衛や孫右衛門のことをいっしんに思っているのが感じられる。人形の演技として端麗かというとそういうわけではないけれど、彼女の想う人々への深い情愛を覚える。そういったことを自然に表現できるのは、やはり清十郎さんならではで、これは天性のセンスによるものだと思う。
孫右衛門の話を聞いているあいだのリアクションもうまい。ひたすら嘆いているだけなので、普通にやったらかなり単調になると思うが、抑揚なのか泣き方自体なのか、真に迫るものがあった。
孫右衛門〈吉田玉也〉の目隠しをはずされたあとの所作は、今回は「外されて即、忠兵衛から目をそらす」になっていた。ここまですぐに目をそらすとなると、お客さんがある程度「目隠しを外す」ことを知っていること前提の芝居ですよね。
「目隠しを外す」演技については過去記事で書いたことがあるが、浄瑠璃本文にはない演出で、昭和戦前期の創出。昭和14年に豊竹山城少掾・初代吉田栄三・吉田文五郎によって発案されたものが紆余曲折ありながら現代に受け継がれている。現代では、目隠しを外すことは「孫右衛門の仕草がチャリっぽくなるのを防ぐ」という山城少掾の意図から遊離し、すでにあたらしい意味と価値を創出している。そのうえで、目隠しを外されたときの孫右衛門のリアクションをどうすべきかは、現代文楽での課題だと思う。この演技の時間をつくるために、梅川が目隠しを外すタイミングがどんどん早くなってきているのではないかという気もするし、今後、どうなっていくのだろう。
孫右衛門は小川の向こうへ去っていく忠兵衛たちを見送るのに必死になって、転倒する。そのとき一瞬、手すりに乗っけた足の甲が見える。このときの草履は、ちゃんと、梅川になおしてもらった、鼻緒に紙のこよりをすげたものになっているのね。可愛い……。本当に一瞬しか見えないけれど、ぜひ注目してほしい。
段切、うずくまって袖なし羽織で顔を覆うのは、これまでの玉也さんのやりかたと同様だった。
忠三女房〈吉田簑一郎〉は、出てくるとすぐ、上手の一間の障子をはたきで掃除しはじめる。最初少しはたいてからムズムズしてちょっと止まり、鼻を袖で覆ってまたはたきはじめる。この小技のさりげなさ……、さすが簑一郎さんって感じ。「すぅぅぅ〜〜べったとやら!!!」のすべりも良かったです。
忠三女房は床の藤太夫さんもよくて、藤太夫忠三女房のあの独特の「ヤバさ」は独特だなと思った。ただのチャリではない「本物」感がある。あれを「無視」するとは、忠兵衛も肝が太い。さすが公金巨額横領するだけのことはある。
しかし、忠三女房から「飯が仕掛けてあるほどに」って言われたのに、梅川も忠兵衛も一切おかまいなしだったが、いまごろ焦げてるんでしょうか。
- 義太夫
口[御簾内]=豊竹亘大夫(前半)竹本碩太夫(後半)/野澤錦吾
前=豊竹藤大夫/鶴澤清志郎
切=豊竹錣大夫/竹澤宗助 - 人形
忠三女房=吉田簑一郎、八右衛門=吉田玉路、亀屋忠兵衛=吉田簑二郎、遊女梅川=豊松清十郎、樋の口の水右衛門[黒衣]=吉田簑悠、伝ガ婆[黒衣]=吉田玉峻、置頭巾[黒衣]=吉田玉征、弦掛の藤次兵衛[黒衣]=桐竹勘昇、針立の道庵[黒衣]=吉田玉延、親孫右衛門=吉田玉也、捕手小頭=吉田簑太郎
■
壇浦兜軍記、阿古屋琴責の段。
この阿古屋の何がいいって、阿古屋〈桐竹勘十郎〉、秩父庄司重忠〈吉田玉志〉、岩永左衛門〈吉田玉佳〉が全員自分の世界でやっている異常空間なことだよね。
お互いなんの協調性もない(disってません)。
ちいかわで言うと、モモンガ、くりまんじゅう、ウサギが好き勝手吼え散らかしてるシーンにしか見えない(disってません)。
おのれらなんじゃ!?っていうこの個性の衝突こそ、文楽、って感じがする。
勘十郎さんが演奏の演技にリアリティを求めているのは、これまでも指摘してきた通りだ。(2019年1月大阪公演、2019年2月東京公演)
意図がとくに顕著にわかるのは、琴の弾き方が人間と同じ点。人形演技の場合、人間の演奏とは逆に、(人形から見て)手前から奥に向かって手を動かすセオリーがあるので、確信的といえる。ほかの人が配役されたときの朝顔(生写朝顔話)などと比較するとよくわかる。
なぜそうしているのか? パブリックには、おそらく、「歌舞伎の阿古屋は本当に三曲を弾くので、文楽でも」という答えになるはず。勘十郎さんは過去に玉三郎を意識したような発言もしていたし、他の演目含めて歌舞伎の見せ方を参考にしている演技が端々にある*1。
しかし、今回の阿古屋を見ていて、実質的にはそれ以外の理由が大きいのだろうなと感じた。
勘十郎さんが阿古屋の演奏の写実性にこだわるのは、本人がかしらの操演よりも右手の演技を重視しているからだろう。勘十郎さんの阿古屋の場合、演奏のあいまの演技のかしらの動きがかなり硬い。かしらの重量に負けているのだと思うが、単調になっている。あえて書くと、簑助さんはもっと「上手い」だろう。人形の演技の本質で簑助さんへ競合することは絶対不可能で、では「阿古屋」は簑助さんがやるよりも「つまらない」芝居になってしまうのか? 「華やぎ」のない演目になっても仕方ないのか? そうならないよう、アトラクション的な演目のアトラクション感のより一層の強調として、得意な右手の芝居をいかした演奏演技へ注力しているのではないだろうか?
右手への優先性については、琴の演奏時が顕著。後列席からだと人形の顔はまったく見えず、異様に伏せた姿になっていると思う(少なくとも、過去上演時の記録映像はそうなっている)。歌舞伎、あるいは実際の琴の演奏家は背筋を伸ばして顔が見える状態で演奏しているはず。本来人形も同じはずだが、客席から美しく見えるように顔をあげた状態に構えると琴の弦に手が届かないから、その見栄えを捨てても手を伸ばせるよう、上体を大きく下を向かせて琴に覆いかぶさっているのではないか。人形の命のはずの顔が見えなくなってもやる執着心はまじで狂ってると思う。
勘十郎さんを天才という人は多い。でも、私は、「天才」のような、持って生まれたセンスだけでものごとをなしとげているニュアンスの言葉を使うには惜しい人だと思う。勘十郎さんが私たちに見せているものの99%は、勘十郎さんの努力に支えられているだろう。いや、なんなら、120%くらいは努力によるものではないか。はたして今後、ここまでの気迫をもつ人は出てくるのだろうか?
その路線で考えると、三味線、胡弓と進んでいくうちにリアリティの練りが抜けてくるのは、なんとも惜しいと感じた。
三味線では胴への右手手首のかけかた、またそれとの弦との関係など、他の人には及び難いリアリティだ。これらは普通は両立できない場合が多いので、かなり研究してやっていると思う。ただ、かしら(目線)を右手に向けているのは、やや不思議。三味線の場合、手元を見るとしたら左手の場合が多いのでは思うが、なぜ。琴のときもほぼずっと右手を見ているのが気になったけど、殊に三味線だと、ふだん三味線さんを見慣れているので、「目線そっちなのか?」と、結構不自然に思った。長唄とかでも、正面見て弾くと思いますけど……。うなだれている表現なのかな?
胡弓はもう一工夫欲しい! 胡弓らしさがいまいちなのは、左手が原因だと思う。胡弓は楽器自体を左右に振るのが演奏上の特徴。振るタイミングそのものは合っていると思うんだけど、振りがほとんどなく、ほんの少しずらす程度になってしまっていた。人形は実際に楽器を弾いているわけではないことを逆用して、大げさにやったほうがいいのではないかと思った。今回の左は本公演の阿古屋は初めての人だと思うが、そうそうすぐには対応できないわな。頑張れ!!!!!
阿古屋の細かい演技で気になったのは、重忠に髪から抜いた簪を差し出す部分。結髪の都合で本当に髪に挿している簪は抜けないので、わざわざ介錯にうしろから簪を出してもらうという面倒な手順があるわりに、かなり形式的な演技のように感じた。昔はもっと意味のある(意味を持たせた)演技だったのだろうか?
重忠は非常に知的でクリーンな佇まい。11月の冨樫の香り高さとは異なる方向の、清潔感と華麗さのある姿。
以前重忠がきたときに比べて研究が進んでおり、今回は人物像のやわらかみを重視しているようだった。じっと白洲を見据えるように位置を低めに構え、阿古屋に目線を合わせて親身に説諭するような姿勢。柔らかく優しげだ。特に阿古屋に話しかけるときにはかなり低めに構えていて、物堅そうにミュッと伸び上がっている岩永と並ぶと、ひとめで役の性質がわかるのが面白かった。
玉志ウオッチャー的には、玉志サンは最近は人形の佇まいに柔らかみが増してますよね。以前は鋭利なところが多かったけど、芝居に余裕が出てきて、全体的に柔らかく、ふんわりもっちりとした弾力がある系の所作になってきている気がする。単にキレがいいだけでは「拙速」にしかならないので、良い。
そして、独自のキラキラ感がかなり高まっていて、ポーズがキマりすぎているのが良すぎた。三味線の音色に耳を傾け、階に右足を下ろして長袴を流し、両手で支えた刀を下ろしてついて、目を閉じ首を少しだけ傾ける姿……。重忠は孔明のかしらでかなり小顔なこともあり、キラッキラにキマりすぎて、絵みたいになっていた(文楽劇場ウェブサイトの、この舞台写真に載っているポーズ)。阿古屋潰す気か? 玉志さんは去年正月の「尼ヶ崎」でも、勘十郎の光秀潰す気か?ってくらいにキラッキラにキマりまくった久吉をやっていたが、この主役ガン無視の1ミリの遠慮会釈もない前のめりぶりは本当にすごいと思った。また、阿古屋に告白を迫ってわずかに前のめりになる姿も、物柔らかさを忘れず綺麗に止まってとても美しく決まっており、わずかな場面にも手を抜かないのが玉志さんらしくて、良かった。
重忠は阿古屋の三味線の演奏の手が止まったとき、注意を促して刀を階に「トン!」と突く。この音にはっとさせられて阿古屋はまた三味線を弾き始めるが、この音で“謎の途中離席をしていた岩永が襖の陰からピョコッと顔を出す。その際、重忠もはっとして後ろを振り向くのだけど、そのタイミングが岩永とまったく合ってなさすぎて、笑った。玉佳さんが出るのが遅いのではなく、玉志さんの振り返りが早すぎるのが悪いんですけど(こういう拙速さは改めて欲しい)、そこも含めて「こいつら気が合ってねえな」って感じで、良かった。もしくは、兄貴風をビュービューに吹かして、タマカ・チャンを早く出させるしかないな!
しかし玉志さん、芸風的に重忠が似合いすぎていて、「ご本人登場」を通り越してカメオ出演みたいになっていた。まあこの人はずっと前から「これ」だから……。と思っていたが、調べてみたら、重忠役、2回目だった。2019年1月大阪公演で出たときが初役だったのか。なんだろう、この比類なき「畠山重忠」の貫禄。
もう一人の「阿古屋潰す気か」、岩永左衛門〈吉田玉佳〉。
玉佳岩永は、リアルにマイペースなおじさんだった。マイペースっていうか、素? 玉男様の六助(彦山権現誓助剣)が玉男様自身であることのように、玉佳さんの岩永左衛門も玉佳さん自身なのかもしれない。
もうねえ、胡弓の真似が、長い。長すぎる。しつこいわ(笑)。火箸を延々カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ言わすのも、勘十郎への嫌がらせかいって感じで、笑ってしまった。文司さん岩永の場合、「火鉢に当たってぬくぬく」「阿古屋を観察」「だんだんフリフリ」「ゴキゲンにまねっこ」「火鉢の炭が跳ねてアチチ」など、小刻みに変化をつけており、あれは相当工夫してたんだなといまさらによくわかり、苦笑いしてしまった。文司さんは、コメディアンとして上手いなと思った。
それにしても、岩永左衛門は、足が相当ユラユラしていた。袴の裾に猫はいっとるんか……?????
あと、タマカ・チャンの熟柿色の肩衣にはめちゃくちゃ笑った。そんな色、岩永左衛門以外いつ着るんだ?????? でも、個人的には好きな色です。
今月良弁の次に動かない人、榛沢六郎〈吉田玉翔〉は、ハナ肇の銅像と化していて、良かった。頑張っとる頑張っとると思った。
水奴ブラザーズは、“お揃い感”がそう見せるのか、『忍たま乱太郎』に出てましたか?って感じで、良かった。時々フォーメーションが変わるのも、なんか面白い。水奴役のご本人たちのうち、上手側の2人は舞台中央にいる人形たちを横目で見られるので、気になる人形を観察しているのが良かった。
今回は阿古屋役が呂勢さんに交代。情念深く貫禄のある錣さんの阿古屋とは異なり、すんなりとした立ち姿がイメージされる阿古屋で、廓の水に慣れた教養ある女性のイメージ。MARCH卒な感じがする。脱毛してそう。
ひとつ気になったのは、三曲が「歌っている」ように聞こえなかったこと。演奏としては上手だと思うんだけど、セリフや地の文との違いがわからなかった。歌唱になっていない感はどこからくるのか。過去の阿古屋役の錣さんは歌っているように聞こえたが、錣さんの場合、地や詞部分の抑揚に強い特徴があり、逆に歌唱部分はスッキリしているので、その差分を感じ取れるからなのか……?
ヤス左衛門はちょっと若い印象だけど、下品さがないのが良い。時折「悪役」を「下品」に語る人がいるが、悪役かどうかと下品かどうかは全く違う。その区別がついていないのを聞くのが個人的にかなりのストレスなので、その意味でも、良かった……。
「阿古屋」の舞台は堀川御所なので、京都。余談だが、「琴責」の決断所のイメージは、江戸時代の奉行所をモデルにしていると思う。岩永は火鉢にあたってヌクヌク参加しているけれど、江戸時代の奉行所の規定では、奉行は「ちゃんと」座っていなければいけないことになっていたそうだ。もちろん、寒くても火鉢禁止。ざえもん……、自由……。
┃ 参考
2019年2月東京公演時、阿古屋についての勘十郎さんのトークショー記事
- 義太夫
阿古屋 豊竹呂勢太夫、重忠 竹本織太夫、岩永 豊竹靖太夫、榛沢 竹本小住太夫、水奴 竹本聖太夫、水奴 豊竹薫太夫/鶴澤藤蔵、ツレ 鶴澤寛太郎、三曲 鶴澤清公 - 人形
秩父庄司重忠=吉田玉志、岩永左衛門=吉田玉佳、榛沢六郎=吉田玉翔、遊君阿古屋 桐竹勘十郎(左=吉田簑紫郎、足=桐竹勘昇)、水奴= 吉田和馬、吉田簑之、吉田玉延、吉田簑悠
■
第三部には、現在の文楽とその技芸員の魅力がよく出ていたと思う。
「新口村」のメンバーのすばらしさは、前述のとおり。このメンバーを得て、あらためて、「新口村」は、現実から離れた「こうであったらいいのに」という虚構の物語だからこそ、人形浄瑠璃特有の純粋性を最大限にいかせる演目だと感じた。
公演全体のバランスでいうと、藤太夫さんや錣さん、清十郎さんは第二部へ回ってほしかったという欲はあるものの、「新口村」をここまでのクオリティで観られるのは、初春公演ならではかもしれない。
「阿古屋」はそれとは真逆の意味での虚構の物語。嘘であるからこその華やぎをどう見せるかという点で、勘十郎さんのアプローチはとても貴重。
そして、玉志さんは、徹底して師匠に近づくことを目指す指向性は勘十郎さんとは真逆の考えでありながら、アウトプットされた状態になると、実は結構近いラインにあるのではないかと思う。
今回の重忠と岩永は、はからずもブルース・ブラザーズ的なことになっているのが良かった(背後霊の話)。玉志サンとタマカ・チャン、日によってランダムで配役逆にして欲しいと思った。
■
2Fロビーに飾られていた阿古屋の人形。




次に人形展示の機会があったら、博物館での仏像展示のように、周囲をぐるっと回れるようにしてほしい。舞台ではなかなか見られない背後アングルも見てみたいです。
- 『傾城恋飛脚(けいせいこいびきゃく)』新口村の段
- 『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)』阿古屋琴責の段
- https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/bunraku/2022/51111.html
- 配役:https://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/02_koen/bunraku/2022/R501haiyaku.pdf